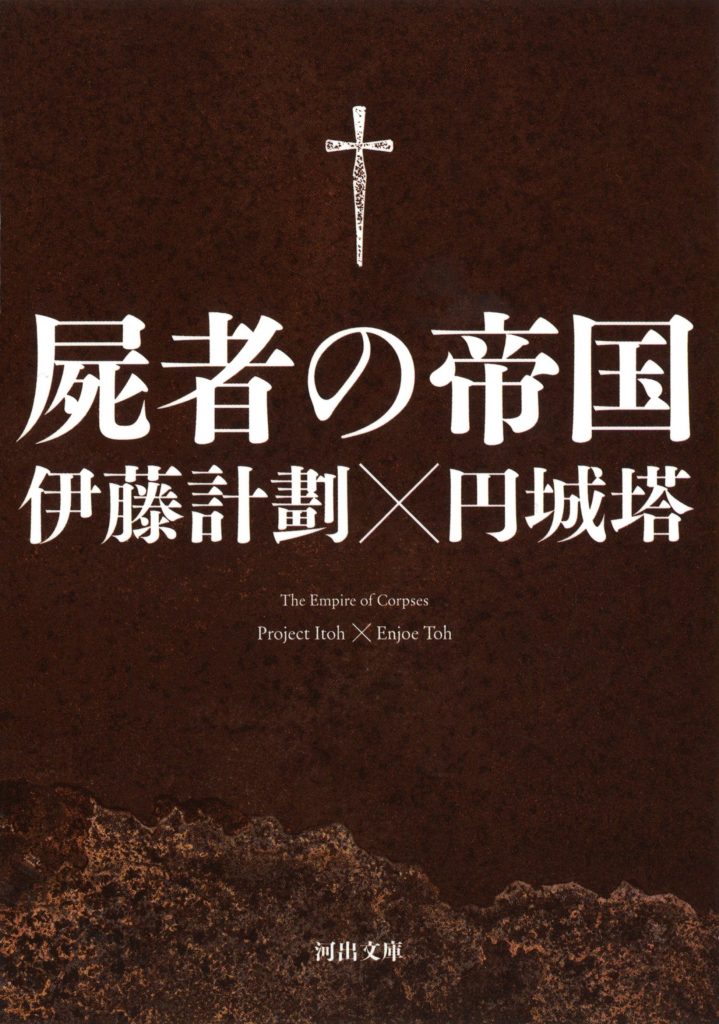屍者の帝国
伊藤計劃と円城塔
この作品には伊藤計劃(いとう・けいかく)氏、円城塔(えんじょう・とう)氏という二人の作者がいる。
そもそもこの作品は伊藤計劃氏が書き始めた作品なのだが、伊藤計劃氏はこの『屍者の帝国』を書き上げることなく、2009年に満34歳で亡くなってしまった。その跡を継いで円城塔氏が完成させた作品になっている。その作品名が『屍者の帝国』という題名であることがやや運命めいて感じられてしまう。
ストーリー
19世紀末―かのヴィクター・フランケンシュタインによるクリーチャー創造から約100年、その技術は全欧に拡散し、いまや「屍者」たちは労働用から軍事用まで幅広く活用されていた。英国諜報員ジョン・ワトソンは密命を受け軍医としてボンベイに渡り、アフガニスタン奥地へ向かう。目指すは、「屍者の王国」―日本SF大賞作家×芥川賞作家が挑む渾身の書き下ろしエンタテインメント長編。早逝の天才・伊藤計劃の未完の絶筆が、盟友・円城塔に引き継がれ遂に完成。
引用:amazon
感想
初読の印象としてはとにかく読みにくい小説という感覚。常に解説を聞きたい。世界観がわからない状態から始まる一人称の物語というのはここまで読みづらいものなのかと驚くほどだ。
しかし慣れてくると、主人公ワトソンのフィルターからみた世界の色味が病みつきになる。それは彼のクールでニヒルな性格と、芯の部分で非常に人間的である魅力がそうさせているのではないかと思われる。読み終わって感じるのは、この物語はあくまでもワトソンのフィルターを通しての物語だからこそ、常に落ち着いた水面のような読み心地でページをめくることが出来るに違いないという事だ。
また、この作品の魅力として挙げられるもののひとつとして時代背景がある。
19世紀末という時代に屍体の蘇生技術が確立されるという仮想の世界の話なので、近未来的で読者置いてけぼりな設定ではなく、あくまでも『屍者』の設定以外は史実を元にしている。その事もこの物語の世界に入った後、抜け出しにくくなる中毒性を生み出すことに一役買っている気がする。
逆に言うと屍者以外は普通の世界ということになる。つまり、この物語のキーワードは『屍者』という言葉になる。
『屍者』とは?
人間の命令をきいて作業することができる。また、脳にインプットしておくことで、膨大なデータも保管できる。高機能のロボット(時に与えられた作業をこなすルンバ、時に膨大なデータを処理できるスマートフォン)のような存在だが、元々は普通の人間だ。死んだ後に屍者として蘇生される。
意思を持たない屍者という存在が特殊な存在として描かれるが、途中で屍者の状態が普通で思考のある生きている状態が異常であるという逆転の考え方も披露されるため恐ろしい。どちらが正しい意見なのかは読み終えた今でもよくわからない。
死体を使ってそのようなことを行うので、自然と物語が欝々としてシニカルな雰囲気になり、作品の魅力を増す役割をしていることは間違いない。
引用の多さ
この物語はさまざまな物語から、多くの物事が引用されている。
僕自身すべてを把握しているわけではないのに、カラマーゾフの兄弟、風と共に去りぬ、シャーロック・ホームズなど、多くの作品から設定や名前を拝借している。引用元を知っていることで楽しめる幅が広がるので、知識の深い方が改めてうらやましく思える。
また、引用ではないが、この『屍者の帝国』ではサラリと書かれた言葉の中に多くの名言が書かれている。いくつか紹介したい。
P212
技術的に可能になってしまった事柄は、感情に訴えることで規制することしかできない
P342
誰かに考えつくことのできた理屈は、他の人間にも思いつくことができる
P359
「あんたは、生命とはなんだと思う」
~中略~
「性交渉によって感染する致死性の病」
達観しているからなのか、皮肉やあきらめのような文章が多いが、同時に本質をついている言葉も多く物語を数段深く掘り下げている。
アニメ
アニメ映画になっているのだが、内容的に変わっている設定が多いようで、原作ファンにとってはどう映っているのか気になるところだ。しかし、主人公たちの姿を動画で見れたら単純に楽しめそうなので是非ともレンタルDVDで観ようかと思っている。
メインのワトソン、バーナビー、バトラー、ハダリー、ザ・ワンはともかく、原作との違いで一番挙がるのはフライデーがただの屍者だった立ち位置から生前からの親友というポジションに変わっていることだ。その方がエンディングに説得力を持たせることが出来るので良い変更点なのではないかと思う。
文庫版あとがきについて
最後になるが、伊藤計劃の死後、引き継いで作品を完成させた円城塔は物語のあとがきにて、
「賞賛は死者に、嘲笑は生者に向けて頂ければ幸いである。」
といった謙虚さと友情に溢れた言葉を残している。
しかし、作品を読み終えた僕の胸は、生者にも死者にも賞賛を送りたい気持ちで溢れている。